
いにしえの都・京都に息づく、茶の湯の文化。その舞台となる茶室の多くは、数寄屋造りという日本伝統の建築様式で建てられています。名だたる茶人ゆかりの寺院で訪ねた茶室は、一見シンプルでありながら、細部にまで趣向を凝らした造り。静かに満たされる感覚“侘び寂び”の心を感じる空間の秘密に迫ります。また、茶室をはじめとする数寄屋造りの建物を手掛ける数寄屋大工を取材。その思いに触れ、日本の職人の高度な技術力について理解を深めていきましょう。
※この記事は広告内容を含みます。
数寄屋造りの茶室を訪ねて、お茶の聖地「大徳寺」へ

京都洛北・紫野の地で鎌倉時代末期に開かれた「大徳寺」は、禅宗のひとつである臨済宗の一派・大徳寺派の大本山です。「大慈院」は、その塔頭寺院。通常は一般公開されていない本堂の奥にひっそりと佇むのが、数寄屋造りの茶室「頓庵」です。「大慈院」には昭和の初め頃に移築されましたが、古くは江戸時代に建てられたといいます。

茶室としては一般的な四畳半の座敷に、招かれた客が背をかがめて出入りする「躙口(ルビ:にじりぐち)」、掛け軸や花入などを飾る「床」、採光だけでなく意匠的な役割をも担う壁面の「連子窓」「下地窓」など、茶室ならではのしつらえが随所に。木や土などの自然素材が、それぞれの素材感を生かしてふんだんに用いられています。そんな茶室に見られる特徴こそが、数寄屋造りを象徴するものなのです。

形のない建築様式? 数寄屋の語源に迫る
茶室に代表される数寄屋造りですが、数寄屋という言葉の由来が気になります。明治時代に京都で創業し、「大徳寺」御用達の看板を掲げる「山中工務店」の稲井田将行さんに伺いました。


稲井田さんによると、「数寄屋の『すき』は、“好き”“数奇”“空き”など、さまざまに書き表すことができます」。安土・桃山時代、茶人たちが前例にとらわれず“好き”なように造った茶室のことを数寄屋と呼んだのが始まり。茶道や和歌など風流なものを好む人を「“数奇”者」と称することから、彼らが自分の思い通りに造ったという意味も込められています。そして、完璧にせず未完成な部分を残す“空き”という解釈も。柱や壁紙などのしつらえや、床の間にいける花によっても部屋の表情は異なります。「未完成だからこそ、完成形は一つではない。数寄屋造りの茶室は一期一会なんです」と、稲井田さん。数寄屋とは建築様式を示す言葉でありながら、自由で決まった形式がないというのが興味深いところです。
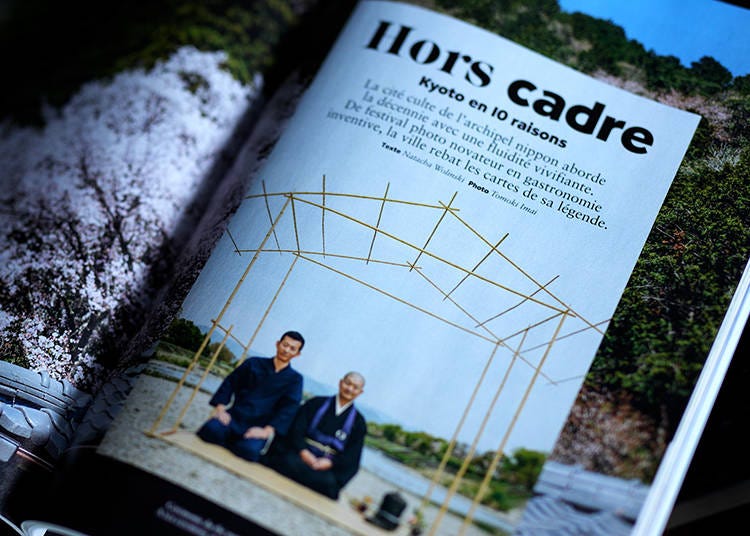
自然の木を自然な姿で。数寄屋造りの特徴とは
数寄屋の語源を紐解いたところで、次に数寄屋造りの特徴を見ていきましょう。
まず一つには、自然との調和があります。数寄屋造りには、杉や檜、竹などの木をはじめとする自然素材がふんだんに使われています。その使い方にも特徴があり、一般的な柱は皮を剥いで四角く製材したものが多いのに対して、茶室をはじめとする数寄屋造りの場合、皮のついたままの丸太を使うことが珍しくありません。


製材や組み立てに手間がかかったとしても、丸太の柱や「面皮柱」をあえて使うのは、素材である木の持ち味を生かすため。だからこそ、室内にいながらにして自然に包まれるような感覚を覚えるのです。また、できてすぐの建物が美しいのはもちろんのこと、経年変化が楽しめるのも自然素材のいいところ。時間が経つほどに新たな表情を見せてくれます。


薄く加工した杉や檜、竹などを平面状に編んだ網代を天井材として使う「網代天井」も、数寄屋造りの茶室の特徴の一つです。使用する素材と、「矢羽根柄」「籠目柄」「亀甲柄」「一松柄」といった編み方の組み合わせにより、さまざまな表現が生まれます。

無駄を省き、簡素にすることも数寄屋造りの特徴。「あまりでしゃばらず控えめだけど、よく見ると手が込んでいる。作り手には、そこに気がついてもらえるかな?という思いもある」という稲井田さんの言葉が印象的です。また、華奢なものが好まれるという京都では、茶室の柱はほっそりとし、障子も極細の木を細かく組んだものが多いのだそう。質素であっても実は洗練されている、京の粋を感じます。
高度な技術と繊細さを兼ね備えた数寄屋大工


一般住宅はもちろん、社寺建築とも異なる数寄屋造りには、特別な施工技術が必要とされます。「山中工務店」の作業場で、京都の銘木「北山杉」の丸太を茶室用の「面皮柱」に加工していたのは、数寄屋造り専門の職人・数寄屋大工の西山さん。その仕事風景を覗いてみましょう。

大工としての西山さんの経歴は約25年。そのうちここ10年ほどは、数寄屋造りの茶室などを専門に手がけています。
まず、斧のような道具「ちょうな」で丸太を粗く削ったら、次に数種類の「カンナ」を使って表面をなめらかにしていきます。「四隅に皮を残す『面皮柱』では、角まで削らない分、隣り合う面と面が直角かどうかを逐一確認します。四角く製材するよりも手間がかかりますね」。


柱の土台に自然石を用いる場合は、ここからさらにひと苦労。カーブした石の上に柱が垂直に立つように、石と柱の接地面をぴったりと合わせなくてはいけません。石の凹凸に合わせて柱を少しずつ削るという、気の遠くなるような作業を繰り返します。このように、数寄屋大工の仕事は、コツコツと地道な工程の積み重ね。高い技術力と繊細さも求められます。

「大工にはいろいろありますが、主に丸太の木を扱うのは数寄屋大工の特徴ではないでしょうか」と、西山さんも言うように、「山中工務店」の作業場にはさまざまな種類の丸太が並んでいます。それらを元の素材の持ち味を残しながら加工するのも、数寄屋大工の大切な仕事の一つ。「木は一本一本風合いが違います。どんな場所に置いたらきれいに見えるか、良さが生きるか。使う場所も木に合わせて考えていくのです」。
茶室の建築には、数寄屋大工のほか土壁を塗る左官職人、戸・障子・襖などを造る建具職人など、さまざまな職人の力が必要とされます。その中でも数寄屋大工は、依頼主である施主の思いを形にするために集まったチームのまとめ役のような存在。幅広い知識と経験が求められます。日本国内で数寄屋大工の数が多い地域は、やはり京都なのだそう。茶室などの数寄屋造りを手掛ける大工になりたいと、「山中工務店」の門を叩く若者もいるそうです。
茶道の広がりとともに、数寄屋造りの魅力も世界へ
茶道はいまや日本国内にとどまらず、世界各国に広がりを見せています。お茶にまつわる文化とともに、茶室に見られる日本伝統の建築様式である数寄屋造りも海を越え、日本文化の魅力のひとつとして注目を集めているようです。
自然素材をうまく活用することで室内に自然を取り込んだ、数寄屋造り。数寄屋大工たちは、身近にあって豊富に手に入る木材を、その個性を生かして大切に扱ってきました。日本人が長い歴史の中で育んできた木との付き合い方。そこには、自然と共存するためのヒントがあります。職人の技とともに日本の木の文化は受け継がれ、これからも発展していくことでしょう。
※価格やメニュー内容は変更になる場合があります。
※特記以外すべて税込み価格です。
-
PR

神々の故郷と進化する旅の拠点:伊勢市駅と伊勢志摩観光の新たな魅力
by: LIVE JAPAN編集部
-
PR

もし京都旅行中に災害が起きたら?知っておきたいポイント徹底紹介!
by: LIVE JAPAN編集部
-

【大阪ヴィンテージ時計】梅田・心斎橋で出会う、世界が認める「中古高級時計」
by: LIVE JAPAN編集部
-
PR

世界遺産・熊野古道「中辺路ルート」への誘い:紀伊田辺駅を拠点に巡る、進化した旅
by: LIVE JAPAN編集部
-
PR

JR奈良駅・近鉄奈良駅周辺 21時以降に営業しているオススメ飲食店4選
by: 寺岡 真吾
-

伊勢志摩の「里・海・森」を育む聖地リゾートへ:三井不動産「NEMU RESORT」2026年グランドリニューアル徹底速報ガイド
by: 寄稿ライター



















